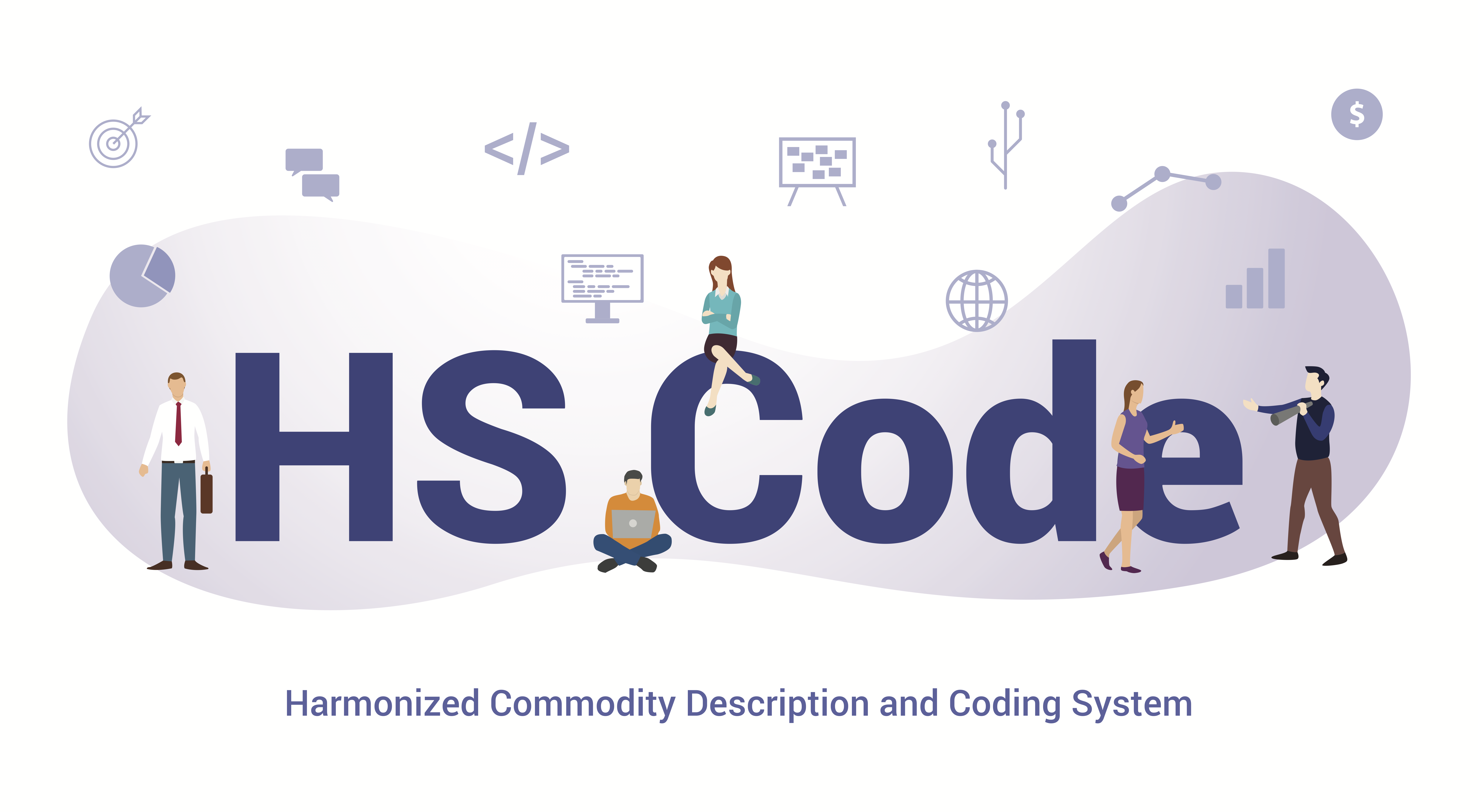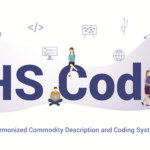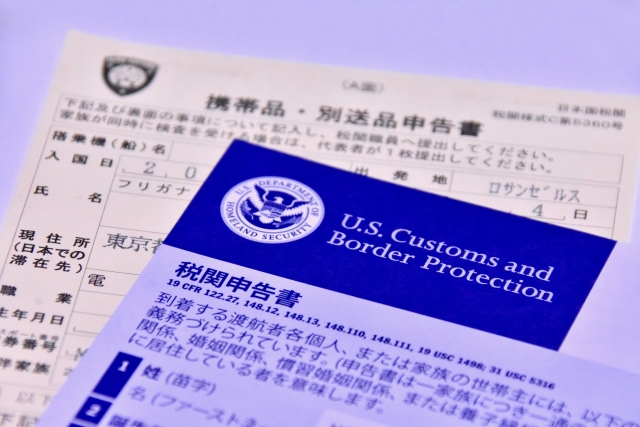

.jpg)
貨物の輸入予定の方やその関係者は、輸入前に税関に対して事前に税番(HSコード)を確認できます。
事前に確認することで、よりスムーズに通関が行えるのもメリットの一つです。
今回は、この「事前教示制度」についてお話しします。
- 事前教示制度の概要・種類
- そのメリット・デメリット
事前教示制度の概要
事前教示制度は、税関に対して下記の内容について照会し、その回答を受けることができる制度です。
関税区分(税番・HSコード)
この関税区分(税番・HS)で事前教示制度を利用される方が多いのではないでしょうか。
価格設定は、重要な要素です。輸入商品に関しては、関税ももちろん商品価格に影響します。
事前に関税率が分かれば、販売戦略の役に立ちます。
税番?HS?と思う方は、次の議事を御覧ください。
原産地
さまざまな商品に「Made in Japan」や「Made in China」等の表記を見たことがあるのではないでしょうか。
人にも国籍あるように、そう、物にも「国籍」があるんです!
この国籍によって輸出入規制や関税率が違うんです。この原産地の確認を税関に照会することができます。
関税評価
関税評価とは、価格を課税標準として関税が課される輸入貨物について、その課税標準となる価格(これを「課税価格」といいます。)を、法令の規定に基づいて計算・決定することをいいます。
税関HP 関税評価用語等解説

貿易に不慣れな人は難しいのではないでしょうか。
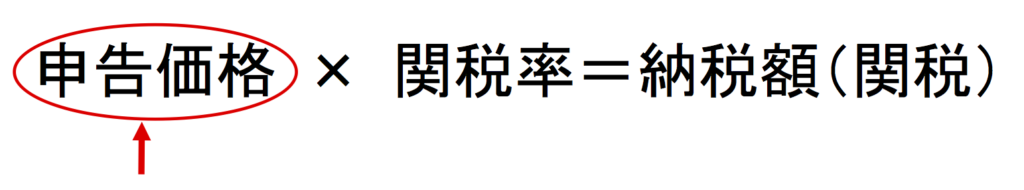
この「申告価格」を法令の規定に基づいて計算や決定することです。
ボールペンを100万円分、海外製造メーカーに注文します。しかし、そのボールペンのインクは、日本製の特殊インク(50万円分)で、海外の製造メーカーにを無償で支給したとします。もちろんその特殊なインクは、ボールペンの価格の一部です。
輸入申告する際は
「ボールペン(100万円)」+「特殊インク(50万円)」=商品代金150万
で輸入申告してください!という一例です。
減免税
関税の減税、免税のことです。さまざまな種類があります。

.jpg)
一度、日本から輸出した貨物を輸出時と変わらない状態で日本に輸入する場合の免税制度(「再輸入免税」)の一つです。
「再輸入免税」とは、関税定率法第14条第10号に規定される「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度です。
税関HP カスタムアンサー
事前教示制度の種類
電子メール・窓口または電話による照会
ある程度情報が不確定でも、参考情報として考えられる税番を回答をいただけます。
注意点は、あくまでも「参考情報」とうことです。
実際の輸入通関時には照会内容と異なる可能性があることを視野に入れといてください。
- カタログ(素材、成分、機能が分かるもの)
- 用途
- 商品写真
<筆者の経験による>
商品によって準備した方がよいものは、異なりますのでご注意を!
利用方法については、下記の税関HP URLをご参照ください。
メールを利用した事前教示制度(関税分類)について
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen.htm
文書による照会
原則は、文書による照会です。この照会から回答書をもらうと原則3年間尊重されます。
また、文書による回答は照会書を受理してから
関税分類(税番)・原産地及び減免税・・・原則30日以内
関税評価・・・原則90日以内
確かに時間が掛かりますが効果は絶大です。税番を確定したけば、文書による照会をおすすめします。
まとめ
筆者の独断と偏見ですがメリット・デメリットをまとめてみました。
| 時間 | コスト | 信頼度 | |
| 書類 | × | △ | ◎ |
| 電話 | ○ | ○ | △ |
| メール | ◎ | ◎ | ○ |
| 窓口 | △ | × | ○(現物持参) |
・書類 何と言ってもメリットは「3年間尊重される」ことです。税番が確定することで通関も通関業者からの確認もなくスムーズに進みます。ただしデメリットとして情報が公開されるとことです。
・電話 時間がない時や情報収集としては有効です。ただし、どうしても電話でのやり取りのため税関としても確認しづらい面もあるのではないでしょうか。
・メール ある程度商品情報があるのであれば筆者はメールをお勧めします。回答も比較的早く、根拠がそれって入れば輸入通関の際も税番の変更は少ないと思います。理由は、税関職員の回答だからです。
・窓口 これはどれだけ商品の情報があるかによると思います。現物や資料があれば信頼度も問題ないでしょうか。窓口に行っても口頭のみであれば、信頼度は低いでしょうか。